はじめに
外国人材の雇用を検討している経営者の方、あるいは、日本での就職を目指す留学生の方にとって、日本の「在留資格」制度の理解は、避けては通れない、最初の、そして最も重要なステップです。
しかし、その種類は多岐にわたり、専門用語も多く、「ビザ」との違いさえも曖昧なまま、情報収集に困難を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、そのような方々に向けて、在留資格の基本的な概念から、主要な就労可能な在留資格の種類、それぞれの取得要件、そして注意点に至るまで、網羅的かつ体系的に解説していきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、外国人雇用や、日本での就労に関して、最低限知っておくべき、正確な知識の土台を、身につけることができるはずです。
まず理解すべき、在留資格と「ビザ(査証)」の根本的な違い
最初に、多くの方が混同しがちな「在留資格」と「ビザ(査証)」の違いについて、明確に定義します。
- ビザ(査証)とは何か?
ビザとは、その外国人が日本に入国しても問題がないことを、海外にある日本の大使館や領事館が確認し、発行する「推薦状」のようなものです。 これは、あくまで「入国審査」のための書類であり、一度日本に入国してしまえば、その役割は、基本的には終了します。 - 在留資格とは何か?
在留資格とは、日本に入国した外国人が、日本国内で、どのような活動を行い、どのくらいの期間、滞在することが許可されているかを示す、法的な「資格」そのものです。 日本での生活の、全ての基盤となる、最も重要な許可となります。
この二つは、目的も、管轄も、全く異なるものです。この記事では、後者の「在留資格」について、詳しく解説を進めていきます。
多岐にわたる「在留資格」の全体像
日本の在留資格は、現在、全部で29種類存在し、それぞれに、日本で行うことができる活動内容が、厳格に定められています。
これらは、大きく分けて、以下の3つのカテゴリーに分類することが可能です。
① 就労が認められる在留資格
大学教授、医師、弁護士、企業の語学教師やエンジニア、熟練の料理人など、特定の専門分野において、その能力を発揮することが期待される外国人のための資格です。この記事では、このカテゴリーを、中心的に解説します。
② 就労が原則として認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在などが、これにあたります。原則として、これらの資格で、収入を得る活動を行うことはできません。(ただし、「資格外活動許可」を得ることで、一定の範囲内でのアルバイトなどが可能になる場合があります)
③ 身分または地位に基づく在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が、これにあたります。これらの資格を持つ外国人は、活動内容に制限がなく、日本人と同様に、原則として、どのような職業にも就くことが可能です。
主要な「就労可能な在留資格」と、その要件
ここでは、特に、留学生からの変更や、企業が外国人を雇用する際に、中心となる、代表的な就労資格を、いくつかご紹介します。
□ 技術・人文知識・国際業務
これは何か?
いわゆる「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれる、最も代表的な就労資格です。理系分野の専門職(エンジニア、プログラマーなど)である「技術」、文系分野の専門職(企画、経理、マーケティングなど)である「人文知識」、そして、語学力を活かす専門職(翻訳、通訳、語学教師など)である「国際業務」の、3つの分野をカバーしています。
主な取得条件
- 学歴要件: 原則として、従事しようとする業務に関連する専門分野を専攻して、大学を卒業していること、または、日本の専門学校を卒業していることが必要となります。
- 職務内容との関連性: 大学や専門学校で学んだ内容と、就職先で従事する業務内容に、密接な関連性があることが、重要となります。(専門学校卒の場合は大学以上に極めて重要となります)
- 日本人と同等以上の報酬: 雇用される外国人が、もし日本人であった場合に支払われるであろう給与額と、同等以上の報酬を受けることが、明確に定められている必要があります。
□ 経営・管理
これは何か?
日本で、会社の経営者や、事業の管理者として活動するための在留資格です。外国人起業家が、日本で会社を設立する場合などが、これにあたります。
主な取得条件
- 事業所の確保: 日本国内に、事業を営むための事務所が、物理的に確保されていることが必要です。
- 事業の規模: 原則として、常勤の職員が2名以上いるか、あるいは、資本金の額または出資の総額が500万円以上であることが求められます。(2025/08の条件です。今後改正される可能性があります)
- 事業の安定性・継続性: 提出する事業計画書などから、その事業が、安定的かつ継続的に行われるものであることが、審査されます。
□ 特定技能
これは何か?
日本国内で、人手不足が深刻な、特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために、2019年に新設された在留資格です。
主な取得条件
- 技能水準: 各分野で定められた「技能測定試験」に合格することが必要です。
- 日本語能力水準: 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格することが必要です。
- 18歳以上であること。
申請における、一般的な注意点
在留資格の申請は、非常に厳格な審査が行われます。以下の点に、特に注意して、準備を進める必要があります。
- 申請書類の整合性
提出する全ての書類(申請書、理由書、証明書など)の内容に、一切の矛盾がないことが、絶対の前提となります。 - 立証責任は、申請人側にある
「私は、この在留資格の要件を、全て満たしています」ということを、客観的な資料に基づいて、申請人(外国人本人または、その代理人)の側が、完璧に証明しなければなりません。 - 過去の在留状況
留学生時代のアルバイトの超過(資格外活動違反)など、過去の在留状況に問題があった場合、審査に、著しく不利な影響を与える可能性があります。 - 素行の善良性(ルールを守ってきたか)
これまでの日本での在留期間において、法律を遵守してきたかが問われます。特に留学生の場合、「週28時間以内」という、資格外活動(アルバイト)の時間が、厳格に守られていたかは、重要なポイントとなります。 - 公的義務の履行状況(社会の一員としての責任を果たしているか)
税金や、社会保険料の納付状況も、審査の対象となります。具体的には、以下の義務を、きちんと果たしている必要があります。
国民健康保険料・住民税・国民年金の加入及び保険料の納付。
これらの、社会の一員としての最低限の義務を果たしていない場合、「日本社会のルールを守る意思がない」と判断され、申請に、著しく不利な影響を与える可能性があります。
まとめ:専門家への相談が、成功への近道となる
ここまで、在留資格の基本的な概念と、主要な就労資格について、解説してきました。
ご覧いただいた通り、在留資格の取得は、多岐にわたる専門知識と、綿密な準備を必要とする、非常に複雑な手続きです。
書類の不備や、要件の誤解によって、一度不許可となってしまうと、再申請のハードルは、格段に上がってしまいます。
外国人材の雇用や、日本での就職を、スムーズに、そして確実に成功させるためには、早い段階で、行政書士などの、入管業務を専門とする専門家に相談し、アドバイスを求めることが、結果的に、最も確実な近道となります。
まずは、ご自身の状況を正確に把握し、事前に、しっかりと準備を進めていきましょう。



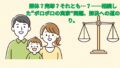

コメント