はじめに
近年、日本社会において、所有者不在の「空き家」の増加が、深刻な社会問題として認識されています。
親から実家を相続したものの、利用する予定がなく、どう対処すれば良いか分からずに、途方に暮れている方も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、そのような状況に直面している方に向けて、相続した空き家を放置することの法務的・税務的デメリットと、その問題を解決するための具体的な対処法を、網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、ご自身の状況に合わせた、最も合理的で、賢明な第一歩を踏み出すための、確かな知識を得ることができるはずです。
なぜ、「空き家の放置」が、最悪の選択となるのか?
まず、最も重要なことからお伝えします。相続した空き家に対して「何もしない」という選択は、将来的に、様々なリスクを発生させる可能性があります。
具体的には、以下の3つの大きなデメリットが考えられます。
デメリット①:経済的負担の増大
空き家は、所有しているだけで、様々なコストが発生し続けます。
- 固定資産税・都市計画税:
建物が存在する限り、毎年課税されます。さらに、適切な管理が行われていないと自治体から判断された「特定空家等」に指定された場合、税金の優遇措置が解除され、固定資産税が最大で6倍に増加する可能性があります。 - 維持管理費用:
定期的な清掃、庭の手入れ、小規模な修繕など、建物の資産価値や、近隣住民の安全を維持するための費用が継続的に発生します。 - 保険料:
火災や自然災害に備えるための、火災保険や地震保険の保険料も、所有者負担となります。
デメリット②:法的責任の発生リスク
空き家の管理を怠った結果、第三者に損害を与えてしまった場合、その所有者として、法的な責任を問われる可能性があります。
- 工作物責任:
老朽化したブロック塀が倒壊して通行人が怪我をした、台風で屋根が飛散して隣家を傷つけた、といった場合、民法上の工作物責任に基づき、所有者が損害賠償責任を負うことになります。 - 失火責任:
放火などにより火災が発生し、近隣に延焼した場合、重大な過失がなければ失火責任は問われないのが原則ですが、管理不行き届きが原因と判断されれば、責任問題に発展するケースも考えられます。
デメリット③:資産価値の著しい低下
建物は、人が住まないと、換気不足や湿気により、驚くべき速さで劣化が進行します。
「いつか売却しよう」と考えていても、いざという時には、建物の資産価値がゼロ、あるいは、解体費用を差し引くとマイナス、という「負動産」の状態になっている可能性も、決して少なくありません。
あなたの状況に合わせた「3つの出口戦略」
では、これらのリスクを回避するためには、どのような対処法が考えられるのでしょうか。
ここでは、大きく3つの「出口戦略」に分けて、それぞれのメリットとデメリットを解説します。
戦略①:『売却』する ―不動産を、現金化する―
最もシンプルで、確実な方法です。
- 古家付き土地として売却
メリット: 建物の解体費用がかからず、現状のままで売却活動を開始できます。
デメリット: 買主側で解体費用を見込むため、売却価格は更地よりも低くなる傾向があります。 - 更地にして売却
メリット: 買主が自由に建物を建てられるため、古家付きよりも高く、そして早く売れる可能性があります。
デメリット: 数十万~数百万円の解体費用が、先行して必要になります。
戦略②:『活用』する ―不動産から、収益を生む―
不動産を手放さずに、新しい価値を生み出す方法です。
- リフォームして、賃貸に出す
メリット: 安定した家賃収入という、継続的な収益源になります。
デメリット: 数百万単位のリフォーム費用が必要になる場合が多く、空室や家賃滞納のリスクも伴います。 - 更地にして、駐車場などとして貸す
メリット: 建物の維持管理コストや、倒壊などのリスクから解放されます。
デメリット: 収益性は、賃貸住宅よりも低くなるのが一般的です。
戦略③:『手放す』 ―所有権を、放棄する―
売却も活用も困難な場合の、最終的な選択肢です。
- 相続土地国庫帰属制度の利用
制度の概要: 一定の要件を満たす土地について、審査手数料と、10年分の土地管理費相当額の負担金を国に納付することで、土地の所有権を国庫に帰属させることができる、2023年4月に始まった新しい制度です。
注意点: 建物が建っている状態では利用できず、更地にすることが前提となります。また、申請しても、必ずしも国が引き取ってくれるわけではありません。 - 自治体や個人・法人への寄付
概要: お住まいの市区町村や、近隣の個人・法人に、無償で不動産を譲渡(寄付)する方法です。ただし、相手方にとってメリットがなければ、受け取ってもらえないケースがほとんどです。 - 空き家バンクへの登録
概要: 自治体が運営する、空き家を「売りたい・貸したい人」と「買いたい・借りたい人」をマッチングさせる制度です。市場価格での売却は難しいが、格安でもいいから誰かに活用してほしい、という場合に有効です。
まとめ:問題解決への、最初の、そして最善の一歩
ここまで、空き家を放置するデメリットと、その具体的な対処法について解説してきました。
多くの選択肢があり、ご自身の状況では、どの方法が最適なのか、判断に迷われるかもしれません。
しかし、どの道を選ぶにせよ、あなたが、今、最初にやるべきことは、たった一つです。
それは、「その不動産の、現在の“本当の価値”と“法的な状況”を、正確に把握すること」です。
まずは、信頼できる不動産会社に「無料査定」を依頼し、その資産価値を知ること。そして、同時に、行政書士などの法律専門家に、権利関係や、法的な規制について相談すること。
その「現在地」が分かって初めて、私たちは、どの出口へ向かうべきか、正しい地図を描くことができるのです。
空き家問題は、一人で悩まず、専門家をうまく活用することが、解決への、最も確実な近道となります。


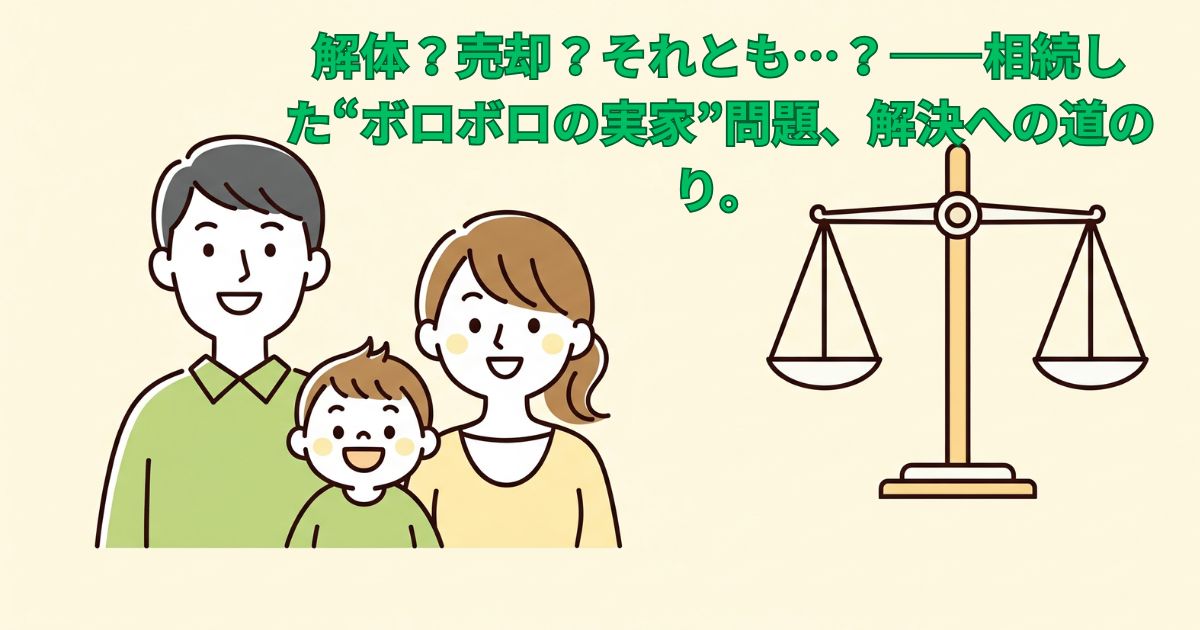


コメント